妊娠や出産は嬉しい出来事ですが、お金のことを考えると不安になることもありますよね。でも、日本には妊娠中や出産時、そして出産後に受け取れるお金や手当がたくさんあります。
この記事では、もらえるお金の種類や申請方法、注意点まで、わかりやすく解説します。
前回の記事はこちらから!
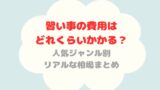
妊娠中に受けられる公的支援・助成制度

妊婦健康診査費用の助成
妊娠中は、定期的に妊婦健診を受ける必要があります。
通常14回くらいの健診が推奨されていて、費用は自治体から助成されます。
助成を受けると、1回あたりの健診費用が無料になったり、一部負担で済んだりします。
自分の住んでいる市町村の窓口で確認しておくことが大切です。
参考リンク:厚生労働省:妊婦健康診査費用助成について
多胎妊婦(双子や三つ子)の助成
双子や三つ子を妊娠している場合、追加で助成金が出る自治体もあります。
妊娠中は医療費が多くかかるので、該当する場合は必ず申請しましょう。
支給額や条件は自治体によって違います。
参考リンク:厚生労働省:多胎妊婦向け助成制度
自治体の出産応援クーポン・給付金
妊娠中や出産後に使えるクーポンや給付金を出している自治体もあります。
母子手帳と一緒に受け取れる場合が多く、ベビー用品や育児サービスに使えます。
どんなサービスに使えるかは、自治体のサイトを確認してください。
参考リンク:妊娠中の自治体支援制度まとめ
出産時に受けられるお金

出産育児一時金
出産育児一時金は、出産した人に一度に支給されるお金です。
健康保険に入っている人が対象で、支給額は約50万円です。
医療機関で直接受け取る「直接支払制度」を使えば、窓口でのお金の支払いを少なくできます。
参考リンク:全国健康保険協会:出産育児一時金制度
出産手当金
会社員や公務員の場合、出産前後に仕事を休むと給与の一部を保障してもらえます。これを出産手当金といいます。
出産前42日(多胎妊娠は98日)と出産後56日までの期間が対象で、給与の約2/3が支給されます。申請には医師の証明書が必要です。
参考リンク:健康保険組合:出産手当金について
医療費の負担を減らす制度
妊娠・出産の医療費が高額になる場合は、高額療養費制度を使うと自己負担額を減らせます。
病院の窓口や保険組合に相談して、使える制度を確認しておきましょう。
参考リンク:厚生労働省:出産育児一時金・高額療養費制度
出産後に使えるお金や手当

育児休業給付金
仕事を休んで育児をする場合、雇用保険から給付金が出ます。
休業開始から180日までは給与の67%、それ以降は50%が支給されます。
勤務先を通じて申請するので、事前に手続き方法を確認しましょう。
参考リンク:育児休業給付金の概要
パパ育休・出生時育児休業給付金
父親が取得できるパパ育休でも給付金があります。
条件を満たすと給与の67%が支給されます。父親も育児に関われる制度なので、活用を検討しましょう。
参考リンク:出生時育児休業支援給付金
児童手当と自治体独自支援
子どもが生まれると、児童手当がもらえます。支給額は年齢や人数によって変わります。
さらに自治体によっては、ベビー用品や医療費に使える支援チケットも交付されます。早めに申請することが大切です。
申請のポイントと注意点

申請期限や必要書類をチェック
給付金や助成金には申請期限があります。
遅れると受け取れないこともあるので、妊娠がわかったらすぐに必要書類を確認して準備しましょう。
会社や病院への確認
出産手当金や育児休業給付金を申請するには、会社や医療機関の証明が必要です。
書類をそろえる前に、提出先や必要書類を確認しておくとスムーズです。
制度の組み合わせと節約のコツ
出産育児一時金、出産手当金、高額療養費制度は併用できます。
また、医療費控除や税金控除と組み合わせると節約にもなります。必要に応じて専門家に相談するのもおすすめ。
妊娠・出産でもらえるお金は多くあります。まずは自治体や健康保険組合の情報をチェックし、もれなく申請して安心して出産・育児に臨みましょう。
まとめ|妊娠・出産でもらえるお金を上手に活用しよう

妊娠・出産で受け取れるお金には、妊婦健診の助成や出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、児童手当など、たくさんの制度があります。
それぞれ金額や申請方法、条件が少しずつ違うので、まずは自分が使える制度を確認することが大切です。
特に、制度をうまく組み合わせることで、医療費や生活費の負担を減らすことができます。
自治体の独自支援やクーポンも忘れずにチェックしましょう。
また、申請期限や必要書類も事前に確認しておくとスムーズです。
これから妊娠・出産を控えている方も、すでに出産された方も、制度を正しく理解し、もれなく申請することで安心して育児に向き合えます。
困ったときは自治体窓口や勤務先の担当者に相談することもおすすめです。賢く活用して、赤ちゃんと家族にとってよりよいスタートを切りましょう。

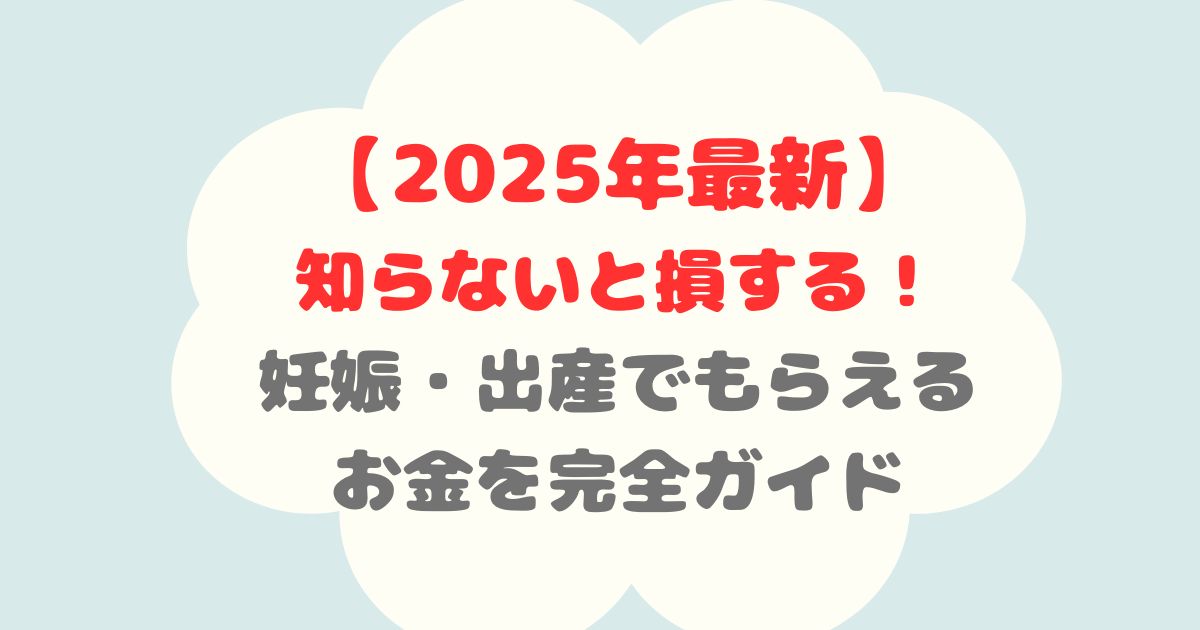
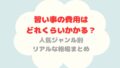
コメント